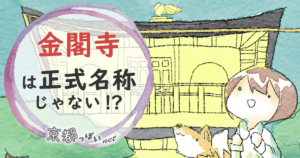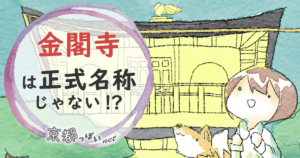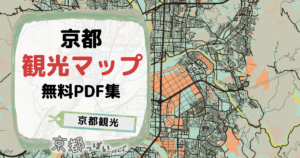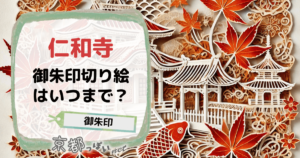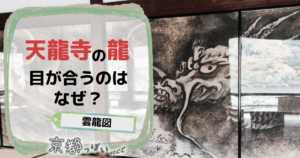京都観光の大きな見どころの一つといわれている金閣寺。見た目のインパクトが強い建造物であることから、国内外の認知度はかなり高いともいわれています。
ではその見どころや豆知識、金閣寺が歩んだ歴史といった、なかなか知られていないであろう部分について、カンタンにご紹介しましょう。
金閣寺の見どころ
時間がなくてもここだけはおさえておきたい、という金閣寺の見どころを簡単にまとめます。
舎利殿(金閣)
1994年にユネスコの世界遺産に登録された金閣寺は、室町時代前期の北山文化を代表する建築物の一つです。
相国寺の塔頭寺院の一つで、正式名称は鹿苑寺です。舎利殿の「金閣」が特に有名であることから、一般的に金閣寺と呼ばれるようになっています。

金閣寺の見どころとしては、なんといっても黄金に光り輝く舎利殿(しゃりでん)が挙げられます。
天気のいい日には、周りを囲む鏡湖池(きょうこち)に舎利殿が鏡のように反射する、美しい景色をみることができます。
舎利殿は、季節や天候によって違う姿を見せます。夏は青々しい緑と、冬は真っ白な雪と黄金色のコントラストに、多くの観光客が魅了されているようです。


舎利殿は、下から寝殿造・武家造・禅宗仏殿造の三層になっていて、二層と三層には金箔が貼られているから、これほどまばゆく光り輝いているんだよ。



これだけ金ピカにしたら悪趣味になりそうなのに、美しくてホレボレしてしまうのは周りの風景との調和ってことよね!
鳳凰


屋根の頂上をよく見ると、鳳凰が設置されていることに気づくでしょう。鳳凰は中国の伝説上の生き物で、権力や永遠の命の象徴とされています。
この鳳凰が設置された理由は、明らかになっていませんが、二つの説があるといわれています。
一つは単に守り神として設置したという説です。
金閣寺を災難等から守り、永遠の繁栄をもたらすよう設置されたといわれています。
もう一つは、新たに徳の高い君子が出現したことをアピールするために、設置したとする説です。
鳳凰は徳の高い君子の出現を予兆する生物といわれています。足利義満は、祭祀権や人事権等の権力を天皇家から摂取したとされており、これから自身が天皇に代わって国を治めていくことを主張するために、設置したのではないかと考えられています。
鹿苑寺庭園


鹿苑寺の境内約132,000㎡(約4万坪)のうち、92,400㎡(約2万8千坪)が特別名勝、特別史跡に指定されている鹿苑寺庭園です。
歩き回って鑑賞する形式の池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)で、中心にある金閣を映しだす鏡湖池(きょうこち)は6,600㎡(約2千坪)。
葦原島(あしはらじま)・鶴島・亀島など大小の島々があり、畠山石・赤松石・細川石などの数多く置かれている奇岩名石も楽しみましょう。
金閣寺の歴史について簡単に説明
金閣寺を作った人、開基は室町幕府3代将軍足利義満とされています。
歴史を簡単に知りたいなら、年表だけでも目を通してくださいね。
金閣寺の歴史年表
| 1397年 | 足利義満が別荘北山第の造営に着手し、舎利殿(金閣)の建設をはじめる |
| 1398年 | 舎利殿(金閣)が完成 |
| 1467年 | 応仁の乱により、金閣などを残して鹿苑寺焼失 |
| 1624年 | 鳳林承章が庭園や金閣の本格的な修復を行う |
| 1904年 | 金閣の解体修理が完了 |
| 1950年 | 金閣が放火により全焼 |
| 1955年 | 再建工事で復元完了 |
| 1987年 | 漆の塗替え、金箔の張替え、天井画と義満像の復元が完了 |
| 1994年 | 世界遺産(古都京都の文化財)に登録 |
修復が繰り返された歴史


金閣寺は1397年に建立されて以来、さまざまな時代の流れの影響や災難を受けています。
1467年の応仁の乱では、多くの建物が焼失しましたが、幸いなことに舎利殿は無事でした。
その後、1469年に大規模な修繕工事が行われたといわれています。1897年には古社寺保存法に基づき、特別保護建造物に指定され、1904年から1906年にかけては解体修理が実施されました。
金閣寺にとって大事件が発生したのが、1950年。21歳の見習い僧であった林承賢の放火により、舎利殿は全焼してしまいます。
これにより、国宝に指定されていた足利義満の像、伝運慶作の観世音菩薩像、春日仏師作の夢窓疎石像等10体や仏教絵巻等の、貴重な文化遺産も焼失してしまいました。
なお、林承賢は裏山で自殺を図りましたが、一命を取り留めたようです。
しかしこの被害を知った全国各地の人々から補助金が集まったことで、1952年に再建工事がスタートし、1955年には修復が無事完了しました。
その後、1986年から1987年にかけて大きな修復工事が入り、漆や金箔の貼り換え作業が行われ、現在の金閣寺の姿になっています。



金閣の中ってどうなってるのかな?



中は壁も天井も金ピカなんだよ。



ひゃーっ!入ってみたいな~



残念ながら内部は非公開なんだけど、一層目の足利義満像と宝冠釈迦如来像は確認できるので、しっかり見てみて!



えっ!肉眼で見られるの?
それは見なくちゃね!
金閣寺の基本情報
| 正式名称 | 鹿苑寺(ろくおんじ) |
| 通称 | 金閣寺 |
| 山号 | 北山(ほくざん) |
| 本尊 | 聖観世音菩薩 |
| 創建 | 足利義満、足利義持 |
| 開山 | 夢窓疎石 |


1994年にユネスコの世界遺産に登録された金閣寺は、室町時代前期の北山文化を代表する建築物の一つで、臨済宗相国寺の山外塔頭です。
正式名称は鹿苑寺ですが、舎利殿の「金閣」が特に有名であることから、一般的に金閣寺と呼ばれるようになっています。
| 住所 | 京都市北区金閣寺町1 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-461-0013 |
| アクセス | 京都市バス 「金閣寺道」より徒歩約3分 |
| 参拝時間 | 9:00~17:00 |
| 参拝料金 | 大人(高校生以上) 500円、小学生・中学生 300円 |
| 所要時間の目安 | 25~35分 |
| 公式サイト | http://www.shokoku-ji.jp/k_about.html |
まとめ
金閣寺の見どころと歴史について、分かりやすく簡単にまとめました。
池泉式回遊式庭園(特別名勝・特別史跡)に建つ豪華絢爛な金閣(舎利殿)は、やはり写真ではなく、実物をしっかりと見たいものです。
雨や雪といったお天気のときも、それはそれで良い雰囲気を味わえるため、悪天候だからとガッカリすることもありません。
四季折々の美しさを堪能できるので、ぜひ何度も足を運んでみてくださいね。