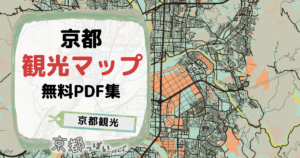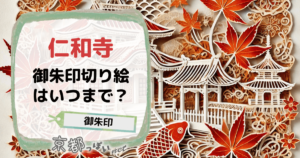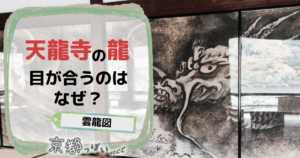京都には古い建造物が多く、世界遺産に認定されている重要な建造物が数多くあります。中でも、京都観光で人気の観光スポットとなっているのが「銀閣寺」です。
銀閣寺を観光するにあたって銀閣寺の特徴や歴史について知っておくと、実りある観光にできることでしょう。
ここでは銀閣寺を観光する際の、見どころや歴史についてご紹介します。
銀閣寺の見どころ
時間がなくてもここだけはチェックしておきたい、という銀閣寺の見どころを簡単にまとめます。
観音殿(観音堂)

銀閣寺へ来たからには、銀閣を見ないことには始まりませんよね。銀閣というのは通称で、慈照寺の中にある観音殿のことを指しています。
観音堂と言われることもありますが、正式名称は「観音殿」です。
現在は銀箔で覆われていますが、建立時は黒漆だったそうです。落ち着いた佇まいでありながらも、花頭窓といわれる飾り窓や屋根上の鳳凰像が風雅です。

銀閣は、金閣や飛雲閣(西本願寺)とともに、京都3名閣といわれているよ。
観音殿は、1489年(延徳元年)に、室町幕府八代将軍の足利義政によって建てられました。義政は、禅の思想を深く信仰しており、観音殿は禅宗の寺院である慈照寺の中心的な建物として建てられました。
二層構造で、下層は書院造りの住宅、上層は禅宗様仏殿です。上層には観音像が安置されていますが、金箔で覆われた金閣寺と比べて、質素で枯淡な趣が漂います。
観音殿は、東山文化を代表する建築物として、世界遺産に登録されています。
なお、銀閣寺は、観音殿の俗称として呼ばれることが多いため、観音堂という名称はあまり使われていません。
庭園の枯山水


また、銀閣寺ならではの枯山水も見逃せません。枯山水は水を使用せず、主に石や砂を用いて山水を表現します。
枯山水は日本庭園を代表する庭園様式ですが、観賞できるスポットがそれほど多くありません。ここ銀閣寺では枯山水が鑑賞でき、風情を感じることができます。
四季折々の景色が楽しめる銀閣寺の庭園は、池泉回遊式庭園です。
錦鏡池を中心として、白砂で作られた波のような模様「銀沙灘」や、富士山の形をした「向月台」など、独特の造形が特徴で、天下第一の名園と呼ばれることも。
錦鏡池
錦鏡池(きんきょうち)は、銀閣寺の中心を占める池です。池の周囲には、白砂で作られた「銀沙灘」や「向月台」などの造形が配置され、独特の景観を創り出しています。
向月台
高さ165センチの巨大な盛り砂の向月台(こうげつだい)は、白砂が円錐形に固められたものです。
錦鏡池の西側に広がる白砂の盛り土は富士山の形をしており、月を眺めながら座って休息するための場所とされています。
銀沙灘
銀沙灘(ぎんしゃだん)は、波紋のようなデザインが施された砂地です。光を反射させて銀閣を明るく照らせるように、といった役目があります。
錦鏡池の北側に広がる白砂の砂紋は波打つような模様が特徴的で、月光に照らされると銀色に輝くと言われています。
本堂(方丈)前から、銀閣(観音殿)・向月台・銀沙灘を眺めることができます。



向月台と銀沙灘をモチーフにした俵屋吉富の和菓子があるよ。これは銀閣寺でしか買えないものなんだ。



銀閣寺でしか手に入らないなら、レアなお土産になりそう♪
境内の自然


銀閣寺は、東山の大自然に囲まれたところに位置します。そのため、銀閣寺の境内には数多くの自然があり、四季によって景色が変化します。
特に、春の桜や秋の紅葉が見られるシーズンの銀閣寺は、数多くの観光客が足を運ぶ人気のスポットです。
紅葉のシーズンを過ぎ雪が降ると、これまでの銀閣寺とは景色が一変。銀閣の屋根に降り積もった雪が日光で光り輝く景色は多くの観光客を魅了します。
境内の東側にある高台から、京都市街の眺めとともに境内全体を見下ろすことができますので、ぜひ上から見下ろしてみましょう。(下記「銀閣寺の基本情報」に写真があります)
銀閣寺の歴史について簡単に説明
銀閣寺を建てた人物は、室町幕府の8代将軍 足利義政(あしかが よしまさ)です。
歴史を簡単に知りたいなら、年表だけでも目を通してくださいね。
銀閣寺の歴史年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1482年 | 足利義政が東山山荘(東山殿)の造営を開始 |
| 1483年 | 足利義政が東山殿に移住 |
| 1489年3月 | 観音殿(銀閣)が完成 |
| 1490年1月7日 | 足利義政が東山殿で死去 |
| 1490年2月 | 慈照院が創始 |
| 1491年 | 慈照寺として寺院に改められた |
| 1900年4月7日 | 銀閣寺が国の重要文化財に指定 |
| 1951年6月9日 | 銀閣寺が国宝に指定 |
| 1952年3月29日 | 庭園が国の特別史跡および特別名勝に指定 |
| 1994年12月17日 | 「古都京都の文化財」として銀閣寺が世界遺産登録 |
銀閣寺を建てた理由
足利義政が銀閣寺を建てた理由には歴史上、室町幕府の財政難が関係しているとされています。
当時の室町幕府は深刻な財政難の状態にあり、将軍の足利義政は幕府を放置して逃げ出すことを考えていたのです。そのため、足利義政は雲隠れをするため、1482年に銀閣寺を建立しました。
銀閣寺を建築したのにはもう1つ理由があり、足利義政の祖父である足利義満の建築した金閣寺をモチーフにしたとされています。
3代将軍 足利義光が幕府の実権を握っていた当時は、幕府の力が絶大でした。しかし、足利義政の頃には既に幕府は衰退していたため、足利義満にすがる思いで銀閣寺を建築したとされています。
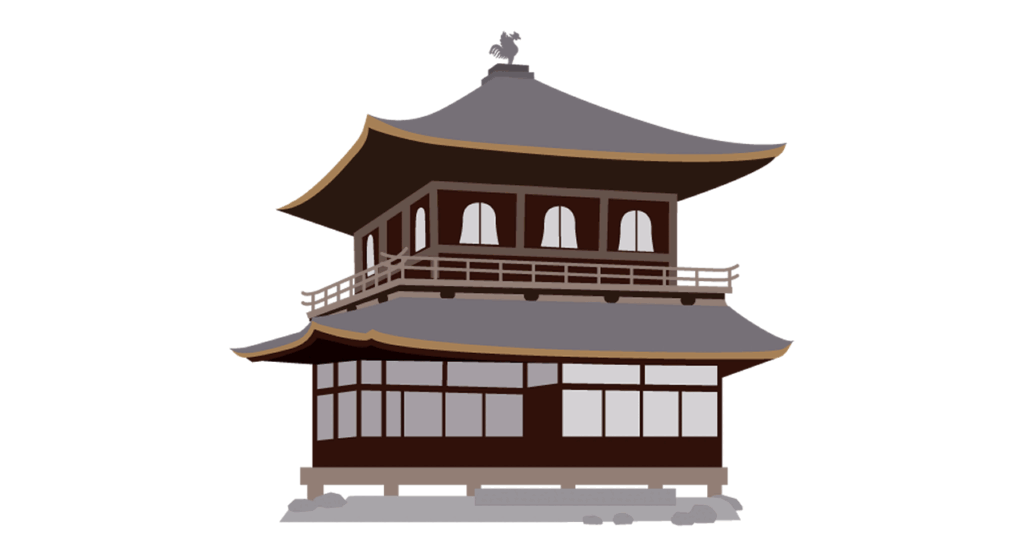
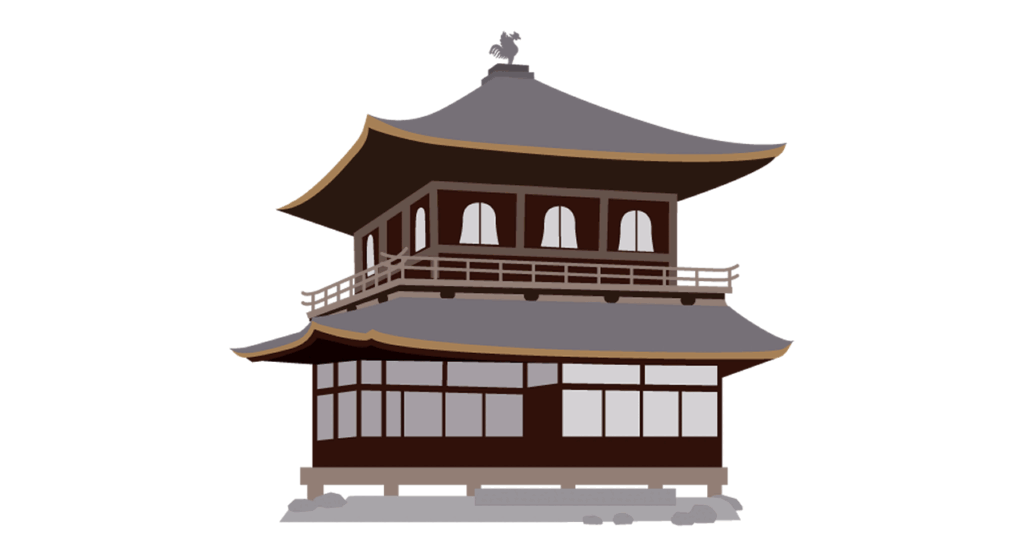
足利義政は完成を見ていない?
銀閣寺における豆知識として、銀閣寺を建設した人が足利義政だということは詳しい歴史を知らない方でも知っているかもしれません。
ただ、足利義政が銀閣寺の完成を見届けてないことを知っていますか?
銀閣寺が完成したのは歴史上1490年2月とされており、足利義政が死亡したのは1490年1月とされています。足利義政は銀閣寺の完成形を見届けることができず、銀閣寺が完成する直前に死亡したのです。
銀閣寺と呼ばれる由来
金閣寺の正式名称が「北山鹿苑寺(きたやまろくおんじ)」であるように、「銀閣寺」の正式名称は「東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)」です。
銀閣寺には一切銀色が使用されていないのに、銀閣寺と呼ばれることを不思議に思う方は少なくないかもしれません。
銀閣寺と呼ばれる由来には諸説ありますが、銀閣寺と呼ばれるようになったのは江戸時代からとされています。銀閣寺には元々銀が貼られていなかったことが調査上明らかになりましたが、当時の幕府財政から考えても銀箔を貼る余裕はありませんでした。
銀閣寺は金閣寺と比べても質素な作りが特徴であることから、金閣寺と対比させるために「銀閣寺」という名前を付けたともいわれています。



足利義政の息子・義尚が若くして亡くなったとき、如意ヶ嶽(大文字山)に点火して魂を見送ったことが大文字の送り火の始まりと言われているよ。



えーっ!?
最初は一人を弔うためのものが、大きな行事になったのねぇ。
銀閣寺の基本情報


正式名称は東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)。
足利義政の東山別荘である銀閣が有名なので銀閣寺と呼ばれています。
ピカピカの金閣寺とは対象的で、一見すると地味に見える銀閣寺。しかし、わびさびが感じられるいぶし銀の美しさは、東山文化の象徴でもあります。
ムダのない美しさは、ミニマリストのお手本になりそうですね。
| 住所 | 京都市左京区銀閣寺町2 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-771-5725 |
| アクセス | 京都市バス 「銀閣寺道」より徒歩約10分 |
| 参拝時間 | 夏季(3/1~11/30) 8:30~17:00 冬季(12/1~2/末) 9:00~16:30 ※特別拝観時は変更があることも |
| 拝観料金 | 大人・高校生 500円、小・中学生 300円 |
| 所要時間の目安 | 30~45分 |
| 公式サイト | http://www.shokoku-ji.jp/g_about.html |
まとめ
銀閣寺の見どころと歴史などについて、分かりやすく簡単にまとめました。
銀閣寺はどのような理由で作られたのか、なぜ銀色じゃないのに銀閣寺なのかなど、現地に行ってからワタワタしなくて済むように、覚えておくと観光に役立つと思います。
本堂(方丈)や国宝の東求堂(とうぐどう)・弄清亭(ろうせいてい)は普段は非公開ですが、春と秋には特別公開されますので、機会があればぜひ訪れてみてください。